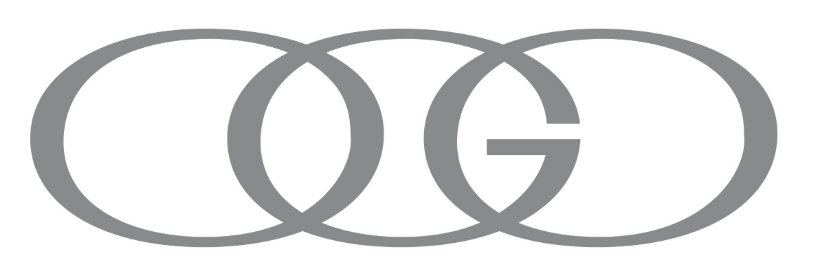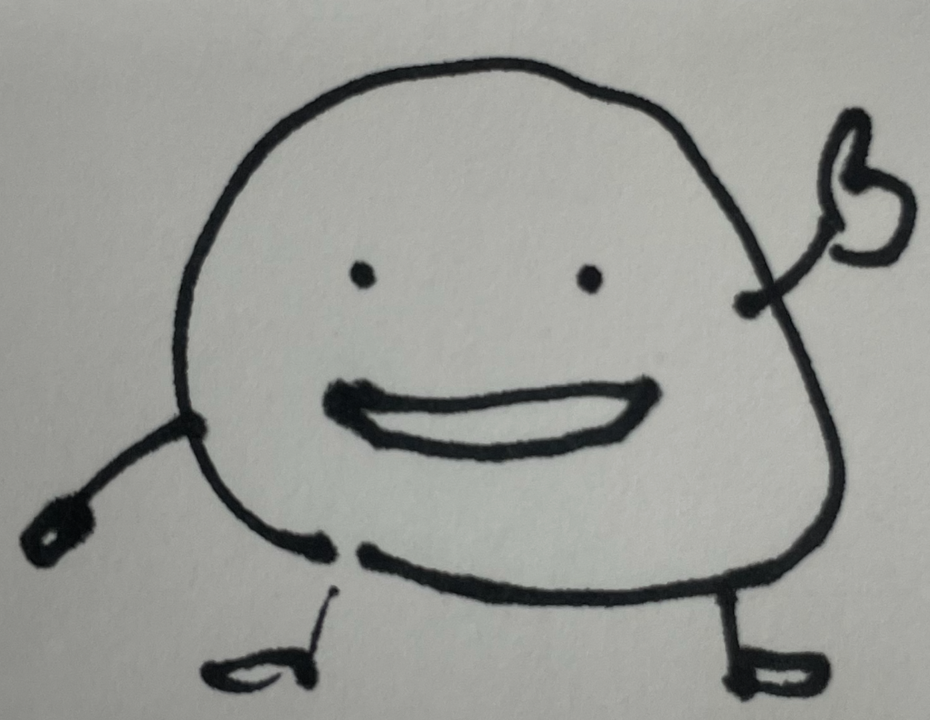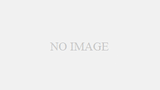言葉は人間の思考の土台です。学びの入り口となります。幼児期にどんな言葉を聞き、どう使っていくかが、その後の学びや人との関わり方に大きな影響を与えます。幼児期に大切なのは、毎日の暮らしの中で「言葉」をたっぷりと味わうことです。
🗣 「くじだ」から学んだこと
孫からもらったお手紙に「くじだが好きです」とありました。最初は何のことかわかりませんでしたが、やりとりを重ねるうちに「くじら」のことだと気づきました。
このように、子どもは耳から聞いた言葉をそのまま覚え、間違いながらも自分なりに伝えようとします。その試行錯誤こそ、言葉の成長のプロセスなのです。
👂 言葉の習得は「耳」から始まる
子どもは1歳半頃から、どこで覚えたのか不思議に思う言葉を口にするようになります。 それがまた可愛い!!
- 名詞は実物を見て覚えやすい
- 形容詞や匂いなど抽象的な表現は体験や繰り返しで理解していく
こうして、子どもは「こんな時に使う言葉なんだ」と少しずつ確かめながら表現を広げていきます。
💡 言葉は考える道具
人は考えるときに必ず言葉を使います。小さな子どもが「どうしよっかな」「こっちにしようかな」と声に出して考えるのは、まだ「内言」が発達途中だからです。
成長すると心の中で言葉を使って考えられるようになります。つまり、言葉は思考を支え、行動や判断を導く力なのです。
👶 言葉が安心感をつくる
赤ちゃんは生まれた時からお母さんの声を聞き、安心感を得ています。
- 名前を呼んでくれる優しい声
- 家族の会話の響き
- 落ち着いた物語や優しいお話を聴くこと
- 子守唄
これらの体験が「安心」と「信頼」の基盤になります。
逆に、苛立った声・言い争いの雰囲気や言葉には、心が傷ついて言葉への恐怖さえ抱いてしまい、不安定な精神状態になってしまいます。
📚 親子の会話が思考の土台に
「これなに?」「どうして?」――子どもの問いかけに、親が答えたり一緒に考えたりする時間が、思考力を育てます。
言葉で気持ちを表現できることは、自信と安心感にもつながります。
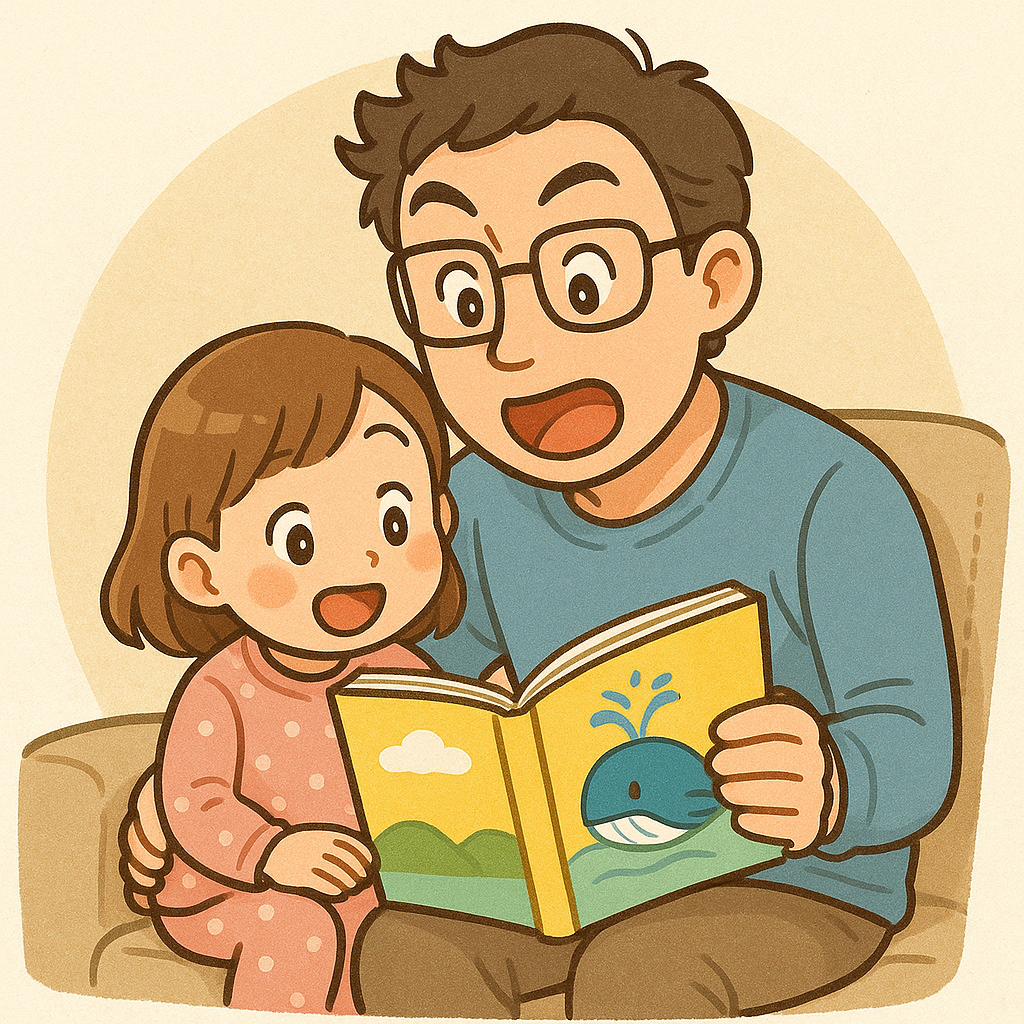
📚 言葉の宝庫=絵本
絵本には子どもが出会うべき豊かな言葉がたくさん詰まっています。 絵本は、子どもの語彙をぐんと広げる宝物です。親子で読み聞かせを楽しむことで、感情を表す力や想像力も育ちます。
○響きのリズム
○擬音語・擬態語
○登場人物のせりふ
読み聞かせを通して、子どもは「ことばの世界」を遊びながら吸収していきます。大人も絵本の読み聞かせを本気で楽しみましょう。
🗣 「話す・聞く・伝える」が学びの基礎
幼児期にたっぷりと
- 話す(自分の気持ちや考えを言葉にする)
- 聞く(相手の言葉を受け止める)
- 伝える(自分の思いを工夫して表現する)
この体験を積み重ねることで、小学校入学後の学びにスムーズにつながります。

まとめ
「くじだ」と書いた孫の手紙から教えられたのは、言葉は間違えてもいいということ。大切なのは、親子で言葉を交わしながら、楽しく豊かに育てていくことです。
言葉は一生の思考の道具。小学校に上がるまでの時期こそ、豊かな言葉のシャワーを子どもたちに届けてあげましょう。
「言葉の力」は、生活の中の会話や絵本、手紙や落書きのような表現から少しずつ育ちます。
親子で「ことば」を楽しむことが、学びの大切な準備=レディネスになるのです。