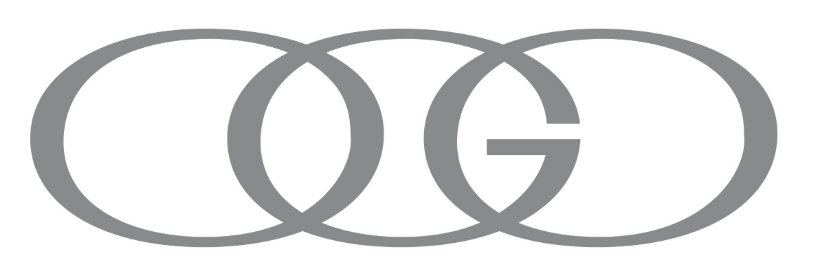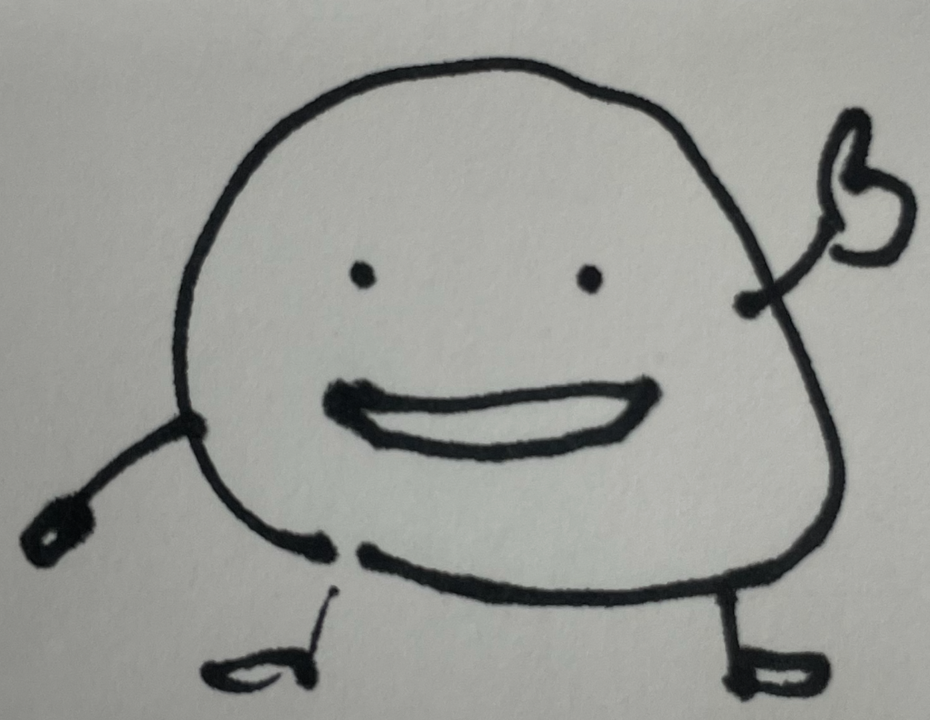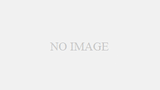- 学習の中で活かせる「 レディネス」の考え方
- 先へ進むことばかりを焦ると、楽しくなくなってしまいます。幼児期には親が一緒に楽しんでいることがやる気につながります。学習の後で一緒に遊ぶ機会に、「なぞなぞ」みたいに問題を出して、復習してみたり、本当に理解できているかをさりげなく「謎解きゲーム」みたいに問いかけてみる!これが、とってもいい進め方・素敵な方法です。
- ①分かったつもりでも、理解できてなかった場合はどうする??学習内容を、一つ手前の段階にもどる。
- ②学習はキャッチボールと同じ!!キャッチボールでは、相手が「よし!こい!」と、受け手として準備ができているかどうかを見極めてからボールを投げます。
- ③子どもを理解するためによく観察すること子どもとの会話や学習の場面を活かして、大人が子どもから学ぶ姿勢はとても大切です。幼児期だけでなく、どの年齢にもレディネスの考え方は、苦手な分野の克服も、新しい知識の定着にも効果を発揮します。
- ④学習もゲームも理解と習熟の深まり方は同じ。先へ先へ進むだけでは理解できていないことを増やすだけ。
学習の中で活かせる「 レディネス」の考え方
学びには順序性があります。それを無視した早期教育などは逆効果です。とにかく早く教えようとしたり、難しい内容や興味のない内容を無理やり学ばせようとするのは、逆効果なのです。
その課題を「学びとして受け入れる準備」がその子にできているか?を見ながら進めることで、無理なく確実に子どもの学びが進みます。これは、特に就学前の幼児期に心したいことです。
子どもの反応を肌で感じ取ることができると、大人の側にもヒントを与えるアイデアなども豊かに浮かんでくるのです。
学びの順序性を考えるためには、子どもをよく観察することが大切です。年齢や経験を考慮したり、学習内容の選択や教え方の工夫が必要になってきます。子どもが面白い!と感じると、無理なく理解が進み、学習することそのものが楽しくなるのです。
先へ進むことばかりを焦ると、楽しくなくなってしまいます。幼児期には親が一緒に楽しんでいることがやる気につながります。学習の後で一緒に遊ぶ機会に、「なぞなぞ」みたいに問題を出して、復習してみたり、本当に理解できているかをさりげなく「謎解きゲーム」みたいに問いかけてみる!これが、とってもいい進め方・素敵な方法です。
①分かったつもりでも、理解できてなかった場合はどうする??学習内容を、一つ手前の段階にもどる。
一つ戻って、再度わかったつもりだった事をやり直してみると、「ああそういうことだったのか」と発見することがよくあります。その発見は自信につながります。理解をするというのは、ただ教えられてわかるものではなく、何度も繰り返し経験してコツが掴めてやっと学習内容の理解が定着するのです。
②学習はキャッチボールと同じ!!キャッチボールでは、相手が「よし!こい!」と、受け手として準備ができているかどうかを見極めてからボールを投げます。
新しい知識を得る仕組みは、キャッチボールの投げ手と受け手の構え方に似ています。新しい知識はボールです。受け手がよそ見したり、まだその気になっていない段階や、グローブをつけていない状態で、超速球を投げられても、受けることはできません。それがレディネスの考え方です。これは生活の中のあらゆる場面や学習内容にも応用できることなのです。
③子どもを理解するためによく観察すること子どもとの会話や学習の場面を活かして、大人が子どもから学ぶ姿勢はとても大切です。幼児期だけでなく、どの年齢にもレディネスの考え方は、苦手な分野の克服も、新しい知識の定着にも効果を発揮します。
④学習もゲームも理解と習熟の深まり方は同じ。先へ先へ進むだけでは理解できていないことを増やすだけ。
(学習も年齢ごとに遊びを工夫するように、個人の関心に則した進め方が一番いいのです。少し頑張れば届く範囲で難しさも織り交ぜて、復習で理解を確かめたり思い違いを発見しながら理解したことを習熟させていく必要があります。)
誰だって、「自分が勝てる・自分は理解できてる」それがやる気になる時です。
ゲームですら「自分ばっかり勝ってても面白くないな」「負けたり勝ったりしてるとやる気が増すぞ」と気づくにはしばらく時間がかかります。学習にも習熟のための時間が必要なのです。わかったことをもっと深めたい・理解したことが実は別の意味もあったと気づくことも必要なのです。
先へ先へ進むだけでは危険なのです。
ここが勉強が遊びや「ゲームと似ているところです。