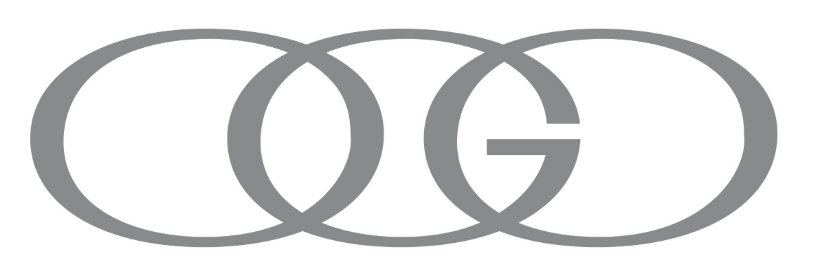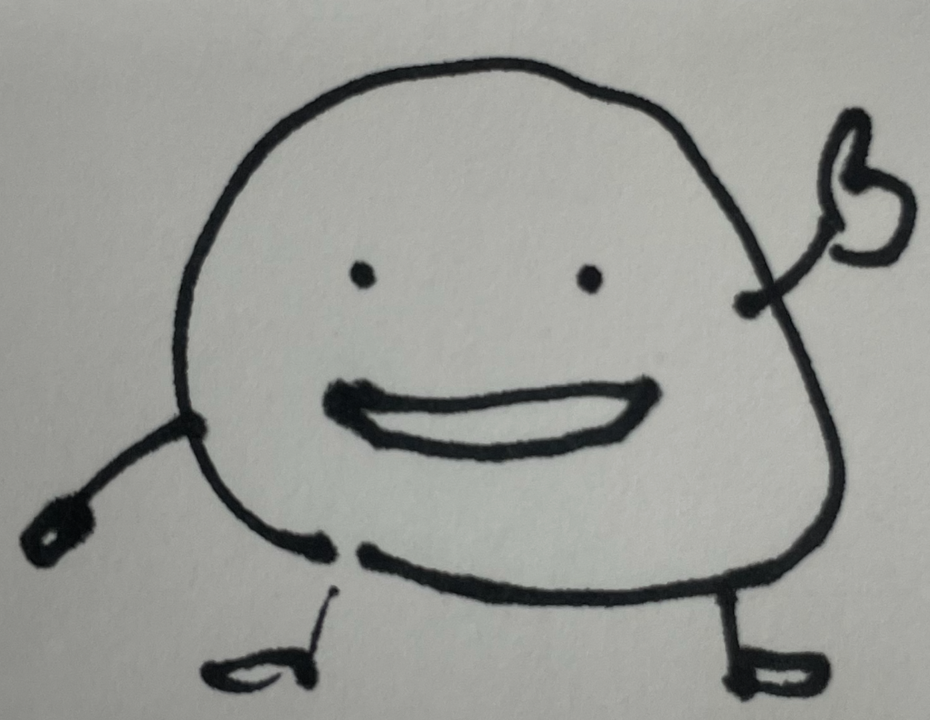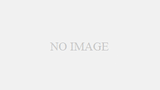🟢 家庭の中で育つ「社会性の芽」
幼児期から社会性は育っています。そこにレディネスを見ることができます。個々の年齢ごとに育っているレディネスを見つけましょう。
家族という小さな社会の中で、まず最初に出会う他者は「お母さん」。
安心できる関係の中で、自分の気持ちを伝えたり、相手の表情を感じ取ったりすることから社会性の第一歩が始まります。
🟢 遊びの中で起こる問題をどう受け止めるか? それが「社会性の練習」
お兄ちゃんと弟の言い分はどちらも本音。友達同士の遊びなら、各家庭での対応も違うため、個々の対応は複雑にもなります。個々の子どものレディネス・各家庭でのレディネスを感じ取るチャンスです。
親の役割はトラブルで「どちらが悪いか」を決めることではなく、
「どうしたらお互い気持ちよく遊べるか」を一緒に考えることです。
家庭の中で生まれる小さな衝突は、社会性を学ぶ絶好の機会です。
🟢 トランプやカード遊びで学ぶ のは [数」や「形」だけじゃなく「心のコントロール」
遊びにはルールがあります。
ルールを守る・譲る・待つ・勝ち負けを受け入れる──
これらの経験が「社会で生きる力」につながります。
🟢 レディネスの考え方
学びには順序性があります。学びとして受け入れる準備ができているか?を見ながら進めましょう。無理なく確実に子どもの学びが進みます。大人のアイデアも豊かに引き出します。
学びに順序性があるからこそ、年齢を考慮したり、まだ難しいようなら、一つ前の段階を経験させてあげる必要があるのです。それがレディネスの考え方です。異年齢で一緒に遊ぶ様子を見ていると、その年齢ごとのレディネスが見て取れるのです。大人が子どもから学ぶ姿勢が、より良いアイデアを生み出せるのです。
例えば、3歳の子と9歳の子が同じゲームをするのは難しいけれど、
大人がレディネスの考え方から「おまけルール」を入れるなどして、遊びの工夫を見せることで、年齢に応じた学びが生まれます。大人が工夫したことを、実体験した各年齢の子どもが、大人を模倣したり、その年齢でできる工夫をしながら、一緒に遊びを作っていく。こうした過程で試行錯誤しながら社会性が身についていくのです。心の安定が自信になって「心のコントロール」ができるようになるのです。

🟢 話し合って決める力が「協調性」を育てる
親子でルールを話し合う。
「どうしたら楽しく遊べるかな?」という対話そのものが、
社会の中で必要な「合意形成力」を育てます。
自分の思いを言葉で伝える力、相手の言葉を聞く力。
どちらも、家庭の会話から育まれます。
🟢 遊びの中から社会へ
兄弟や友達との関わりの中で、
「ズルはいけない」「思いやりが嬉しい」と感じる瞬間があります。
家庭での社会性の経験が、保育園・学校・地域社会へとつながり、
「人と生きる力」を支えていきます。「合意形成力」はとても重要な社会性の力です。