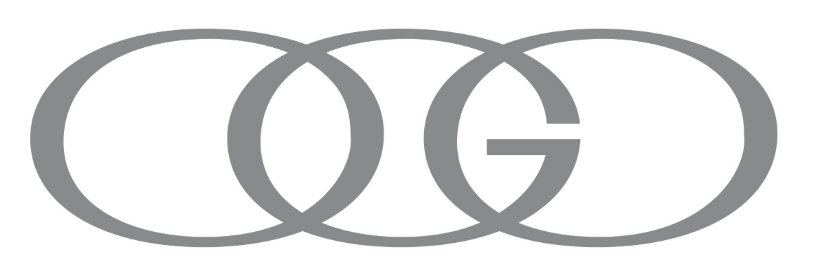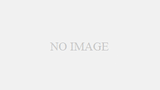心を育てる「衣食住」は、人間にとって安心感の基本です。各家庭の生活リズムを整えることで、子どもの自立心や自信を育むことができます。今回は、幼児期に大切にしたい「生活リズム」について考えてみましょう。
親の背中を見て育つ子ども
- 幼児は、親やきょうだい、友達、テレビで見た人など、身近な人の行動をまねながら成長します。
- 特に「褒められている姿」を見たり体験したりすると、「自分もやってみたい!」という気持ちが強くなります。
- 親子で会話し、生活を共にすることが、安心感や意欲の土台になります。
- 幼児期の学んだことを、子どもは思春期など成長の段階毎に試しながら成長します。親と同じ姿を想定してみるのも、日々必要かもしれません。
睡眠のリズム
- 朝すっきり起きて一日を元気に過ごすこと。
- 仕事や保育園に遅れず到着できること。
- 帰宅後は入浴や食事で心身を整え、夜は質の高い睡眠で疲れをとること。
➡️ 「自分の健康を守る生活習慣」 が自然に身につくことが大切です。将来自分自身の心も身体も大切にする子どもに育てましょう。
排泄の習慣

- トイレの使い方も、自立した後こそ、こまめに教えていきたいことです。
- 外出先のトイレは家庭とは大きさも形も異なり、触れる場所も多様。だからこそ、家庭での声かけや工夫が大切です。
- トイレットペーパーの適切な使い方や捨て方、清潔な扱い方は、小さなことですが生活力の基礎。
- 将来的に初潮を迎える時や、生理用品の扱いにもつながり、「次に使う人が不愉快にならない配慮」を自然に学んでいけます。
➡️ 排泄の習慣は「自分を大切にする心」と「相手への心配り」の両方を育てます。

準備・片付けの習慣
- 「はさみはどこ?」「汚れ物はどこへ?」といった疑問を、ルール化することで家族全員の安心感が生まれます。
- 家族のルールが整えば、指示されなくても自分で行動できるようになります。
- ただし「家庭内ルール」と「社会一般のエチケット」があまりに違うと、外で困ることも。
安心できる居場所
- 子ども部屋の有無ではなく、「ここに座れば安心」「ここで食べる」「ここで遊ぶ」などの家庭の中での定位置が心を安定させます。
- 決まった場所・時間があることで家族の結びつきも深まります。

現代の課題:電気とデジタル機器
- 昔は日が暮れたら寝て、日の出とともに起きる生活でした。
- 今は電気や携帯、テレビで夜更かしが増え、疲労や集中力の低下を招きがち。
➡️ 幼児期から「機器との付き合い方」を整えていくことが重要です。 - 電気機器との付き合い方は親子で真剣に話し合って、ルールを決めていかないといけない時代になりましたね。
- 皆さんの工夫をお聞きしたいところです。
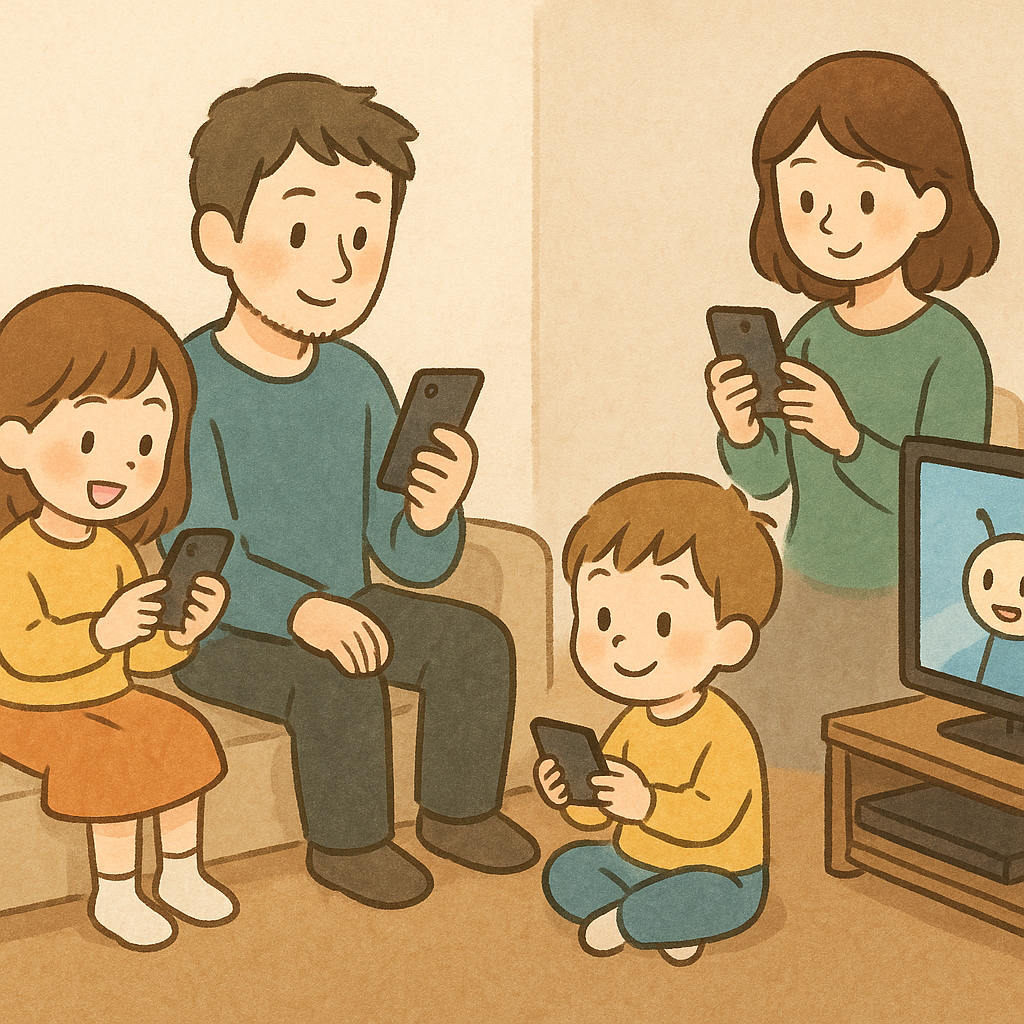
まとめ

生活リズムは「安心感」「自立」「家族の信頼関係」を育みます。
排泄や睡眠、片付けなど、日々の小さな積み重ねが子どもに「自分を大切にする心」と「他者への心配り」を育てます。
家庭で自然に育んだ習慣が、学校生活や社会での適応力の土台となるでしょう。